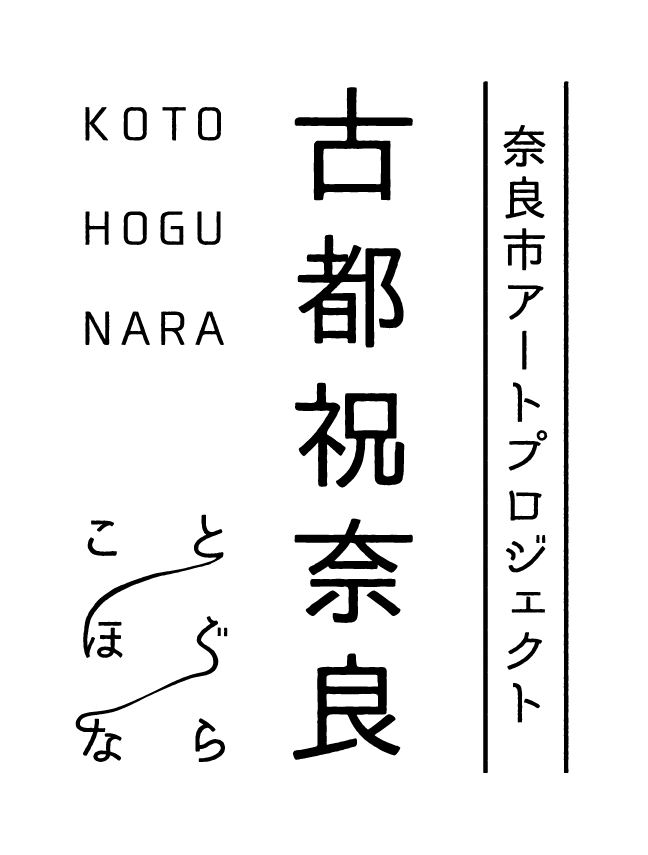トピックス
TOPICS
[参加募集]『古都祝奈良シンポジウム』
©中川容邦/KADOKAWA
まちと未来をみんなで考える
-メディアアートの可能性-
「東アジア文化都市 2016 奈良市」の10周年を記念し、
2026年から新たなアートプロジェクトを始動。
奈良の未来をともに考えませんか。
***
第1部 アーティストトーク
メディアアーティストで、大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーを務める落合陽一さんが、自身の活動や奈良市の文化的資源とのコラボ、奈良市アートプロジェクトへの期待等について語ります。
PROFILE
落合 陽一 OCHIAI Yoichi
メディアアーティスト、筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長、筑波大学図書館情報メディア系准教授、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)テーマ事業プロデューサー。
1987年生まれ、2010年頃より作家活動を始める。境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開。近年の展示として「ヌル庵:騒即是寂∽寂即是騒」(Gallery & Restaurant 舞台裏, 2024)、「昼夜の相代も神仏:鮨ヌル∴鰻ドラゴン」(東京 BAG-Brillia Art Gallery-, 2024)、「どちらにしようかな、ヌルの神様の言うとおり:円環・曼荼羅・三巴」(岐阜・日下部民藝館, 2024)など多数。
第2部 パネルディスカッション
「きたるべき奈良市アートプロジェクトに期待すること」をトークテーマにパネルディスカッションを行います。
森山 朋絵(メディア芸術キュレーター/東京現代美術館学芸員)※予定
安藤 英由樹(大阪芸術大学アートサイエンス学科 教授)
大谷 智子(大阪芸術大学アートサイエンス学科 准教授)
仲川 げん(奈良市長、奈良市アートプロジェクト実行委員会委員長)
PROFILE
森山 朋絵 MORIYAMA Tomoe
1989年より学芸員として東京都写真美術館の創立に携わり多数の映像メディア展を企画。東京大学、早稲田大学、東京藝術大学、バウハウス大学、UCLA等で教鞭を執り、2007年より現職。独ZKM、米MIT、Getty 研究所に招聘滞在後、Prix Ars Electronica 審査員、SIGGRAPH Asia 2008 議長、NHK日本賞審査員、文化庁メディア芸術祭アート部門主査、文化審議会専門部会委員等を歴任。日本バーチャルリアリティ学会フェロー。
***
安藤 英由樹 ANDO Hideyuki
1974年岐阜生まれ。2008年大阪大学大学院情報科学研究科准教授、2020年大阪芸術大学アートサイエンス学科教授。XRの分野を中心に錯覚利用インタフェース、Wellbeingを実現する情報技術などの研究に従事。基礎研究に加え、芸術表現としての先端的科学技術の社会貢献にも関心を寄せ、自らも作品制作を行なう。第12回文化庁メディア芸術祭優秀賞、ARS ELECTRONICA PRIX Honorary Mention受賞(2009, 2011) 等。
***
大谷 智子 OHTANI Tomoko
インタフェースやデジタルコンテンツの心理学的評価を行うと共に、当該分野の理解増進事業に従事。研究者やデザイナーらと共に、錯覚を楽しみ、その利用・応用の可能性を考える錯視ブロックプロジェクトを行っている。この活動は第 11回キッズデザイン賞子どもたちの創造性と未来を拓くデザイン部門優秀賞(経済産業大臣賞)を受賞した。様々な角度や大きさの図形が起こす目の錯覚 (錯視) で、私たちが街に対して無意識に感じている活動的な雰囲気をあらわした「錯視地図」シリーズは、東京都現代美術館や長崎県立美術館等で展示された。
開催概要
日時:2025年3月1日(土)14:00-16:00
場所:奈良市ならまちセンター 市民ホール(東寺林町38)
定員:300人(全席自由)
参加無料・要申込
応募方法
以下のいずれかの方法でご応募ください。多い場合は抽選となります。
Ⅰ. 申込フォームでのご応募 ➡ 申込はこちらから
【申込フォーム締切】2025年2月24日(月)
Ⅱ.往復はがきでのご応募
イベントタイトル、住所、氏名(ふりがな)、電話番号、あればEメールアドレス、参加希望人数を書いて、2月14日(金)必着で奈良市アートプロジェクト実行委員会事務局(〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1-1 奈良市役所文化振興課内)へ郵送。
【往復はがき締切】2025年2月14日(金)必着