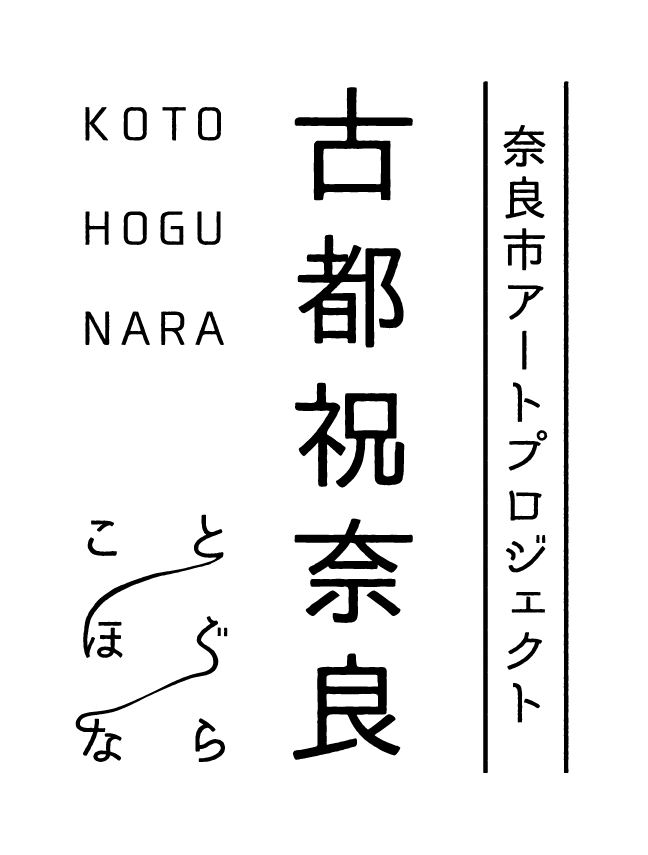トピックス
TOPICS
[レポート]『古都祝奈良シンポジウム』第1部 Artist talk 落合陽一
令和7年3月1日(土)に、奈良市ならまちセンター市民ホールにて開催の『古都祝奈良シンポジウム まちと未来をみんなで考える―メディアアートの可能性』第1部、メディアアーティスト落合陽一さんによるアーティストトークのダイジェストをお届けします。

©2024 Yoichi Ochiai / 設計:NOIZ / Sustainable Pavilion 2025 Inc. All Rights Reserved.
|大阪・関西万博2025のシグネチャーパビリオン
まず、大阪・関西万博2025で私が手がけるシグネチャーパビリオン「null²(ヌルヌル)」についてお話しします。このパビリオンの大きなテーマは「鏡」です。外観から内装まで“鏡”をキーワードにした空間を作ろうとしていますが、チーム内では大きく分けて「外側」と「内側」の二つの仕事を進めています。
外側は、まさに鏡で構成された建築で、周囲の風景を歪ませながら映し出すような外観を想定しています。一方、内側では、人間がデジタルに変換されていく過程を体感できる“デジタルヒューマン”関連のコンテンツ(仮に「ファイリング」という呼称にしています)を制作中です。建物に入ったときの体験として、「自分自身のデータがデジタル空間へと取り込まれていく」感覚を味わっていただきたいと考えています。
この企画自体は2020年頃に立案しました。当時は皆さんご存じの通り、新型コロナウイルスの流行に伴い、多くの人がマスク生活を送り、自宅で過ごす機会が増えていた時期ですね。その頃、生成AI(ジェネレーティブAI)の処理速度が飛躍的に向上していて、たとえば140字程度の短いテキストであれば、2分ほどで小説風に生成してくれるようになり始めていました。そうした技術の延長で、「人間そっくりのAIを作ったらどんな存在になるのか」というプロジェクトを進めたいと考えたのが一つの大きなきっかけです。
さらに、万博開催まで5年ほど猶予がありましたので、「建物を素材から作る」というアイデアにも挑戦しようと思いました。結果として、今回の万博では8つのシグネチャーパビリオンが登場するのですが、そのうち“芸術”分野の発想で関わっているのは、私のパビリオンくらいかもしれません。ほかはロボット工学や先端技術など、さまざまな領域からの参加があり、「この命輝く未来社会のデザイン」という大きなテーマのもとでそれぞれが企画を作っています。私たちのパビリオンは「命を磨く」という提案をもとに、“鏡”を通して命やデータ、存在を再考できるような展示にしようとしているわけです。
|万博と美術
実は、日本における「万博」と「美術」には深い結びつきがあります。たとえば1867年のパリ万博に日本は初めて輸出産業として参加し、その頃に“ジャポニズム”という言葉が生まれました。日本の工芸品が海外で高く評価され、浮世絵などが印象派画家に大きな影響を与えたことは有名です。その後、ウィーン万博に明治政府として公式参加した際に「ファインアート(美術)」という概念と本格的に出会ったと言われています。
そもそも日本においては、襖絵や工芸、仏像制作などが長らく生活や宗教行事の一部であり、“アート”という言葉でわざわざ切り出して呼称しなくても機能していました。しかし、万博を通じて海外の価値観を知り、“ファインアート”というジャンルを改めて社会の中で定義する動きが起こったのです。いわば、日本では「万博の方が先にあって、美術がその後に意識化された」という側面があるわけです。
|1970年の万博
1970年に開催された大阪万博(日本万国博覧会)は、アジアで初めての万博でした。戦後のアジア地域が国際社会から注目を集め始める中で、日本がアジアを代表して開いた意欲的なイベントだったのです。約6400万人という当時としては驚異的な動員を記録し、「♪こんにちは~」というテーマソング(正式タイトルは「世界の国からこんにちは」)が広く親しまれました。
また、技術や科学を通じて社会をどう良くしていくか、さらには地球規模の課題をどう解決できるかが大きなテーマとなり、各国首脳や大統領クラスの要人が来場しては、6か月にわたって議論を交わすような国際会議的な場にもなっていました。国ごとに大掛かりな展示を持ち寄り、外交や文化交流の役割を果たしたのも当時の万博の特徴だったと思います。

|デジタルネイチャーって何?
私自身の専門領域でもある「デジタルネイチャー」という言葉についても補足します。辞書的には「物理的な世界と計算機の中の世界が相互に浸透・融合した結果、従来の“自然”や“人工”という人間的な境界が消滅した状態」を指すと説明されることがあります。もう少し分かりやすい例で言えば、VR(仮想現実)とリアルな空間が相互にスキャンされて、どちらも双方向に実体化するような状況が「デジタルネイチャー」の典型的なイメージと言えるでしょう。
あるとき、「VRに入りたい人はたくさんいる」と言われましたが、それならば「VRの世界から出てきたい人が現れたらどうするのか?」と問いかけてみたのです。実際に、入りたい人はVR空間へ入り、逆にそこから出てくるキャラクターもいるかもしれない。そのとき「そもそもVRとは何か?」と学生に尋ねたら、「それは自然の一部ですね」という答えが返ってきたんですね。これが私の考える「デジタルネイチャー」的な発想です。デジタルと自然が不可分となり、VRも現実も区別が相対化されていくわけです。
|自然は計算機
よく引用されるのは、ノーベル物理学賞受賞者のリチャード・ファインマンが「自然をシミュレーションしたいなら、自然そのものを計算機として用いるしかない」と述べたというエピソードです。たとえば量子コンピュータの開発、あるいは自然界の現象をそのまま計算に利用するアプローチなどがこの考え方に通じます。落ちるリンゴの時間をストップウォッチで測るより、実際にリンゴを落として観測する方が“計算が早い”という話も、同じような発想です。
私自身、修士論文の時代から15年ほど、コンピュータ上で物理世界をシミュレーションし、そのシミュレーションをもとに実際の物体を動かすといった工学的研究を続けています。デジタル空間(コンピュータ)の中にあるデータと、物理的(アナログ的)な形がリンクして動く。そこにこそ「計算機は自然」であり「自然は計算機」であるという考えが如実に表れるのです。
|動く表面
たとえば茨城県の芸術祭で、シャボン玉に映像を映し出す作品を作ったことがあります。シャボン玉は透明なので、そのままだと映像が突き抜けてしまいます。そこで超音波を使ってシャボン玉の背後の空気を振動させ、高速で揺らしてやると、シャボン玉の表面に映像が写るようになるのです。こうした技術的な実験は私の修士論文でも扱っていたテーマの一部で、表面が常に動き続けたり、変形したりする現象に強い興味を持っています。
2020年になると、万博の計画を正式に提出するタイミングが来ました。そこで「鏡面を持ちながら動く表面」をパビリオンの基盤にできないかと考え、鏡面性を維持する樹脂膜や金属膜を振動させ、外観そのものが絶えず歪む建築案を練り始めたわけです。これが今回の「null²(ヌルヌル)」にもつながっています。
|仏像と「null(ヌル)」と「空」
私には“プロフィールを仏像化する”という取り組みをしたことがあります。これは「データ(情報)が形に変換され、再びデータに戻る」という循環を体現する作品づくりの一環でした。東洋的な思想の中では、仏や音楽、そして哲学的な議論でしばしば「空」という概念が登場しますが、私はこれをコンピュータ用語の「null(ヌル)」と重ね合わせて捉えています。
「空即是色、色即是空」の思想を、「何もない」を意味するプログラミング用語の“null”になぞらえ、○、△、□といった記号で表す。そうすると、あるシンポジウムでインド政府の方から「それは五輪塔と同じ思想ですね」と指摘をいただいたのです。○、△、□を見て即座に「ウォーター、ファイヤー、アース」という五大要素を連想されて、本当に驚きました。これは私が「空⇒形⇒空」という流れを大切にしていることにもつながります。
|計算機自然神社
仏像を作った翌年に「神社」を作るプロジェクトも手がけました。日本の神社は「自然信仰」から始まっていて、大きな木や岩そのものを神として祀ることがあります。開祖や教義以前に“そこにある自然”を崇拝するというのが日本的な信仰の原型ですよね。ならば、計算機を自然そのものと見なす「計算機自然」の世界でも、神社が作れていいのではと思ったのです。コンピュータでプログラムを書くとき、私たちはある種の祈りにも似た気持ちでエンターキーを押す瞬間があると思います。そういう祈りの対象や儀式の場を「計算機自然神社」として形にしたわけです。
|我々が命と呼んでいるもの
スマートフォンを見れば、亡くなった祖父母や親戚の写真や会話ログが山ほど残っている時代です。AIの進歩により、彼らの声や姿かたちを再現することが当たり前になる未来がすぐそこまで来ているかもしれません。AIが会話ログを学習し、故人そっくりに喋り始めると、何をもって「命」と呼ぶのかがあいまいになっていく可能性があります。
日本人は元々、自然のあらゆるものに命(霊性)が宿ると考えてきたところがあるかもしれません。したがって、スマホの中で祖父母が“生き続ける”世界が到来しても、ある意味では自然に受け入れる土壌があるとも言えるでしょう。一方で、それを悪用して“オレオレ詐欺”のような犯罪が拡大するかもしれないという懸念もあります。こうした点も含めて、“技術が発展する中で命とは何なのか”を改めて考える好機に差しかかっているのではないでしょうか。
|サン=テグジュペリと死生観
『星の王子さま』で知られるサン=テグジュペリは、「道具は徐々に存在感を失っていき、やがて自然物のように手になじむ形へと落ち着くだろう。そして、人間の意識からも機械という概念が薄れていく」という主旨の発言をしています。飛行機乗りらしい比喩で、とても示唆的ですよね。
機械が自然の一部になり、かたちが消えていく。その展望は90年代以降によく語られるようになりましたが、サン=テグジュペリはそれよりもずっと早い時期に洞察していたのです。そして、デジタル技術がさらに浸透していく現代では、とりわけ死生観が変化すると私は考えています。スマホのデータを通じていつでも故人に“会える”ようになる時代、あるいはAIが人間の仕事や知的活動の多くを担う時代に、「人が生きる」とはどういうことか、「人間とは何か」という問いが深刻化していくのです。
AIが東大入試に合格できるような現状を踏まえると、「なぜ高校生は数学を勉強しているのか?」と疑問を抱く人も出てきます。一歩突き詰めれば「人間はなぜ生きているのだろう?」という根本的な問いに行き当たるでしょう。西洋的な合理性だけでは割り切れない部分があり、それこそが「死生観の変容」や「人類の新たな意味づけ」につながると思います。2200年頃の人類からすれば、人間もウイルスも地球も「計算している存在」として同列に見えるかもしれませんが、いまの私たちは「計算だけではない、感情がある」と主張する。このギャップをどう埋めるかも大きなテーマです。
|最後に
実際に作品をつくる際には、デジタル技術と手作業の両面を組み合わせることが多いです。たとえばコンピュータで計算した図面をもとにプラチナプリントを作るとか、和紙職人から取り寄せた紙を使ってインスタレーションを構成するといった具合に、超アナログな工程と高度なデジタル処理とを行き来します。
そう考えると、東アジアに古くから根付く「空(くう)」の思想――「空」から「形」が生まれ、「形」が再び「空」に戻るプロセスを数千年かけて深めてきた感覚――は、現代の「計算機自然」の時代でもなお、非常に示唆的だと思います。1960~70年代には仏教思想と現代美術が融合した動きがありましたが、デジタル化によってそれが新しい形で再発明されるとも言えます。「古くて新しい、そして新しくて古い」ものが見出され、私たちの認識や創作のあり方を問い直しているのです。
私のパビリオン「null²(ヌルヌル)」も、まさにそうした「どこからが空で、どこまでが形なのかわからない」ようなあり方を目指しています。ぜひ皆さんにも、この“ヌル”な状態――境界が曖昧になり、存在や命が再定義される世界――を一緒に考えていただきたいと思います。